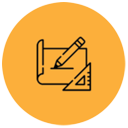六波羅蜜の教えを広めるときの6つの心構えとは?
もくじ
六波羅蜜の目的
八正道が法華経を伝えて広める前の心がまえとすると、六波羅蜜(ろくはらみつ)は法華経を伝え広めるときの心がまえになります。
六波羅蜜は、個人が法華経の教えを広めるときに心がけるべき6つのことです。それは、
① 布施(ふせ) ② 持戒(じかい) ③ 忍辱(にんにく) ④ 精進(しょうじん) ⑤ 禅定(ぜんじょう) ⑥ 智慧(ちすい) |
これらの6つです。
六波羅蜜~1.布施(ふせ)
六波羅蜜でいう布施とは、教えを広めることです。一般的には布施は、ものを与えたり、ほどこしをすることをいいますが、どちらかというとものを与えるイメージが強いですね。
ですので、「法華経を布施する」とは、法華経のおしえを広めることを意味します。
布施で気をつけないといけないことは、伝道するときに「よこしま」な考えを持たないことです。たとえば、法華経を説いてお金を稼いでやろうとか、金品を要求するとかです。
こういう人がいるとしたら、人を利用して自分の利益をむさぼる人なので気をつけてくださいね。
それから、教えを広めるときには法華経を正しく理解し、人に法華経の内容を正しく教えることです。教えを聞く人も法華経が最高の経典で、世の中でもっとも価値のあるものということを分かっていなければなりません!
法華経はものすごく尊いものです。だから、誰でもいいから教えを広めていいわけではないんです。法華経が法華経の尊さがわからない人に法華経を説いてはいけません。
教えを伝道するときは、相手を選んでください!そうでないと教えが汚されてしまうからです。
六波羅蜜~2.持戒(じかい)
六波羅蜜でいう持戒とは、字のとおり戒律を持つことです。
自ら八正道を守りながら人に法華経を正しく説かないといけません。法華経を説いている人が言っていることとやっていることが違ったら信用されるわけがありませんね。
戒律とはやさしく言うとルールと罰みたいなもので、自分に決めごとを決めてそれを破らないように自分をコントロールすることです。
つまり、自ら善いおこないをしながら正しく法華経を伝え広めることが伝道する人には求められているのです!
六波羅蜜~3.忍辱(にんにく)
法華経を広めるときに、ほかの宗教を信じている人から何かと言われることがあります。自分の信じているものが正しいと思いこんでいるため、人を非難したり攻撃したりするんですよ!
いろんな人が法華経を説いたり学んだりする人にいやがらせをしたり、変なことを言ったりするわけです。
今の時代、とくにインターネットだと発信する人の顔もわからないので、そういう誹謗中傷は受けやすいんです。
しかし、誹謗中傷やいやがらせに反論せず、グッと我慢するのが六波羅蜜の忍辱です。相手の言っていることに反応して怒ってはいけません。相手はこちらを言い負かそうとしているので、ケンカに乗らないことです!
この世界、つまり三次元の世界では、善が存在するために悪があります。そのため、さまざな悪いことがおこるわけです。
逆にいうと乱れている三次元世界だからこそ、法華経を広める価値があり、法華経を広める仕組みができているんです。うまい事できてますね。
また、ギャンブルやゲーム、エンタメ、グルメなども八正道や六波羅蜜には必要のないものです。こういったものが習慣にならないようガマンしましょう。
そして、つまらない付き合いをして時間をムダにしないようにしましょう。少しでも変だと思ったら近づかないようにし、付き合ったりすることのないよう注意してくださいね。
ちょっとストイックかもしれませんが、それくらい法華経に集中するとストイックがストイックでなくってしまうんです。それが自然になってしまうんで全然ストイックとは思わなくなります。
六波羅蜜~4.精進(しょうじん)
精進は世間一般に使われるので聞いたことがあると思います。意味は、精一杯努力する、一生懸命になる、必死でやることです。
たとえば、「より一層精進します」とか、「稽古に精進する」などです。
六波羅蜜でいう精進とは、法華経を伝え、広めることに集中することです。そのためにも八正道を守ることは言うまでもなく、法華経に集中し、理解し、相手に分かりやすく説明することが必要ですね。
とくに法華経を読んで考え、さらにポイントになる文章を暗記して考えるようにしましょう。
たとえば、学校の先生が授業で教えるときは前もって教科書を読み込んで、生徒に教えるポイントを暗記してわかりやすく説明できるようにしていますね。それと同じことです。
これに加えて、法華経をもっと深く理解し、尊い気持ちをもって法華経を学ぶことです。つまり、法華経の伝道のためにあらゆる努力をする。これが六波羅蜜の精進です。
六波羅蜜~5.禅定(ぜんじょう)
六波羅蜜の禅定とは瞑想することです。
この世の中は、誘惑にあふれていて、人は楽な方に流れてしまいがちです。あらゆる誘惑や欲が法華経に取り組む気持ちを邪魔します。
誘いに引き込まれるその先には堕落が待っています。そうなると六波羅蜜どころではないですね。人は楽な方に流されますからね。
そうならないようにするには心を落ちつかせるようにします。そのためには、目を閉じて静かな気持ちをにならないといけません。波のない湖の、鏡のような水面の静けさ。それが瞑想なんです。
六波羅蜜~6.智慧(ちすい)
智慧は「ちえ」とも読みます。知恵は、アイデア、ひらめき、直感で、六波羅蜜の「智慧」は解脱して真理を理解し悟ることです。
言いかえると智慧は法華経のことになります。解脱して、如来に帰依(きえ)してビッグバンを起こす方法を授かるのが法華経です。
このひと通りの流れてが書いてあるのが法華経なので、法華経に集中して学ぶことが智慧を身につけることになるわけです。
六波羅蜜のまとめ
六波羅蜜の6つの要素
1. 布施
2. 持戒
3. 忍辱
4. 精進
5. 禅定
6. 智慧
六波羅蜜をまとめると、自分のおこないを正しくして法華経を学び、たとえ非難、中傷があってもそれに耐え、瞑想して心を落ち着かせて教えを広めることが六波羅蜜になります。
まちがった教えを広めること、まちがった人に教えを伝えることはもちろんダメなことです。川を下るのは簡単で、上るのは難しいように、人は楽な方に流されてしまいがちです。
ろくに勉強もせずにいい加減なことを言っていると、教えがどんどん変わって最後は暴力と破壊を生み出すようになってしまいます。こんなことは絶対さけたいものですね。
そうならないためにも、人に法華経を語る前に日ごろから六波羅蜜を思い出して法華経を学ぶようにしてください。
関連記事