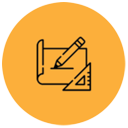六師外道の六人の師は誰?外道の意味とは?
もくじ
なぜ六師外道というのか?
外道とは、真理ではないウソの教えのことをいいます。お釈迦さまが生きていたころと同じときに、六人の精神的な指導者がいたのですが、その六人の指導者のことを「六師」といいます。そこからまちがった仏教の教えを広める六人の指導者たちをのちに「六師外道」というようになったんです。
外道六人の指導者たち
お釈迦さまが生きていたおそよ2,600年前のことです。お釈迦さまが悟りをひらいてたくさんの信者たちを引き連れるようになりました。
ところが、それを快く思わない6人の指導者がいました。それは、ほかの仏教の団体の指導者で、プーラナ、マッカリ、アジタ、パクダ、マハーバーラタ、サンジャの六人です。
これが六師外道の六師です。
かれらは、運命は決まっているから何をしてもダメだとか、何も認めないし否定もしないとか、人は亡くなるとなにも残らない、悪いことをしても魂に変わりはないなど、いわゆるこじつけやデタラメ、へりくつのような考えを持ち出してウソの教えを広めたのが外道の六師でした。
それでも彼らは教団をもち弟子もいたんですよ。まちがった教えについて行く人もいたので怖いことですね。
六師外道の外道とは?
外道とは「外の道」と書きますね。字のとおり、「道をはずれた教え」が外道です。
お釈迦さまが生まれる前から仏教の教えはあったんですが、それが時代とともに堕落して、もともとの仏教の教えの「宇宙の始まりと完成」を説くものとはまったく別の教えになってしまったんです。
不幸なことに、お釈迦さまが生まれたときには、仏教の教えもすでにめちゃくちゃになってしまいました。
今ではもともとの仏教の教えが「南無妙法蓮華経」や「南無阿弥陀仏」などと題目をとなえたら極楽浄土に行けるとか、ツボを買ったりお金を寄付したりすれば幸せになれるとか、自分が得するようなことを言うようになったんです。まあ、ウソの教えですね。それが外の道です。
仏教の伝道を邪魔する人を犬畜生、餓鬼、破壊者とか言いますが、これも外道のことです。
外道の反対の内道とは?
ちなみに、外道の反対で「内道」という言葉があります。
わたしたちが頭で考えることは「思考」といいますね。思考はわたしたちの精神の中にあります。精神が思考を生み出すと言ってもいいでしょう。わかりやすく言うと、精神という入れ物の中から思考が生まれる、となります。
実はあなたの思考はある仕組みによって生み出されているんですよ。それは仏法という仕組みです。
仏法とはかんたに言うと如来の教えのことで、如来の教えがあなたの思考を生み出し、生み出した世界のひとつがこの世界というわけです。この仕組みが仏法なんですよ。
つまり、この如来の教えが「内道」となります。内道こそが仏教が伝えようとしたことです。
六師も内道がわかっていれば道をはずれることもなかったでしょう。ところが、六師はこれがわからなかったということですね。困ったもんです。
外道の本性
外道は、悪いエネルギーをもった悪魔なんですが、六師たちもそれをわかってないんですよ。そういう人はいつの時代にもいて、今もいるでしょう?
まさに地獄から来たような人たちです。
このような人は、本当の教えを見下したり、軽べつしたり邪魔したりしますよね。その心の底にはしっとや「ねたみ」があるからそういうことになってしまうんですよ。
よくこんなことを考えたもんだと思いますが、おかげで仏教の本当の教えがネジまげられてしまいました。
六師は、言ってもみれば性格が悪い人みたいになってしまいますが、それだけではすまないんですね。
今でもその考えは残っていて宗教としてインドに残っています。ちなみに、法華経は宗教じゃないですから!法華経を読めばわかりますよ^^
六師外道のまとめ
六師は、お釈迦さまの時代に生きた六人の精神的指導者のことでした。しかし、この六師はまちがった仏教の教え、つまり「外道」を広め、人々をまちがった方向に導いています。
それだけでなく、本当の仏教の教え、つまり「宇宙の始まりと完成」を教えることなく、真理を伝えることを邪魔していたのです。
さらに、お釈迦さまの教えをねじ曲げて、教えが危ないものだとか、怪しいだとかと言うようになったんです。
ところがお釈迦さまは、六師外道や仏教を破壊するような者にたいして驚かず、毅然として落ち着いていたのです。
本当の教えを広める者にたいして、それを邪魔したり、破壊しようとしたりする者が必ずいるのですが、それらは自滅することがわかっていたのでした。
さすが、お釈迦さまです!
本当の教えを広める者にとって迫害やいやがらせはあります。
法華経を広める者にとって、どんなにさまたげや苦しいこと、混乱があってもそれにくじけることのない強いきもちが必要ということですね。
関連記事